死ぬほど分厚く(ハードカバー全後編でどっちもレンガ、もしくは文庫で5冊)、展開は遅く(レンガ1冊読んでも話が佳境に入らない)、登場人物はめちゃくちゃ多いです(ひとつの村の住人が全員巻き込まれる群像劇)。その癖異様なまでの中毒性を持ち、レンガを2冊読み終えるまで、下手すると読後数日あなたは使い物にならなくなります。
小野不由美が1998年に発表した「屍鬼」はホラー、ミステリどちらとしても高い水準を持ちつつ、高い文学性も併せ持つ驚異的な傑作です。
「屍鬼」あらすじ
人口1300人の小さな村、外場村。外部からは1本の国道しか繋がっておらず、周囲から隔離され、土葬の習慣も未だ残っている。そんなある日、山入地区で3人の村人の死体が発見された。村で唯一の医者・尾崎敏夫は、このことに不信感を持つが、村人達の判断で事件性は無いとされ、通常の死として扱われた。しかし、その後も村人が次々と死んでいき、異変は加速していった。
引用 – Wikipedia
徐々に異常性を深めていく事態の中で、住人たちは薄々「何かおかしい」と感じつつも、それを口にすれば異常な状況を認めることになるため。無意識に現実から目を逸らしてしまいます。比較的現状を性格に把握している敏夫は事態に対して「伝染病ではないか」と疑いを持ち、既存の感染症を調査しますが、該当する症例を見つけることができません。
そもそも進行の速度が異常かつ、初期症状がただの貧血にしか見えないのです。少し顔色が悪かった住人が、三日後には呼吸を止めている。
敏夫の幼馴染である住職の室井静信は、罹患患者が死ぬ直前にとる「ある行動」に異常性を嗅ぎつけますが、追い詰められた敏夫は聞く耳を持ちません。しかしそれは後に重要な意味を持つ符号となり……。
感想(ややネタバレ)
作中で何度も提出されるのは、「ウチと外」「住人とよそ者」「聖と俗」「マイノリティとマジョリティ」、あるいは「人と屍鬼」という対立構造です。
ややネタバレじみてきますが、読者はこの小説を読み進めるうちに、何度もその立場を問われることになります。一見か弱く、庇護するしかないように見えた弱者が同時に加害者でもある。異常な性質を持つ誰かを排斥し、その存在を許容しない。
これは外場村だけの問題ではなく、前科持ち、移民、高齢者、障害者、喫煙者、妊婦、無職、あらゆる人が様々なレッテルを貼られ、否応を問わずウチと外のどちらかに組み込まれることになる現実を色濃く反映しています。だからこそこの物語の加害者の嘆きは胸を打ち、正義を振りかざして手段を問わない敏夫は頼もしい存在であると同時に、どこか狂ったキャラクターとしてしか物語の中に存在を許されないのです。
そしていっそ痛快なほどの滅びの美学。終盤、畳み掛けるように訪れる絶望的な展開はいっそすがすがしいほどです。
「読後数日あなたは使い物にならなくなります」と書きましたが、コミカライズ、アニメ化もされてますので、そちらに走ると一ヶ月ぐらいは優に吹き飛びます(内容は小説版と一部異なる)。
あとがき
「屍鬼」のご紹介でした。
「本当に面白い小説」ではこういう、あなたの都合を無視して時間をゴッソリ奪う作品を紹介していく予定です。早く読みたくて電車の中でハードカバー版読んでたら腕攣りそうになりました。


















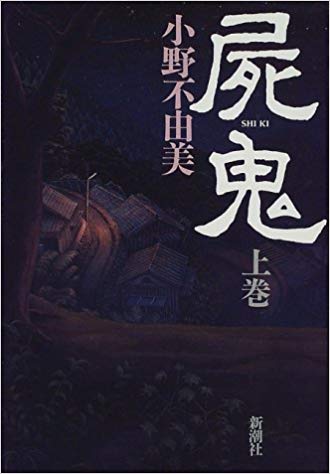





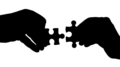
コメント